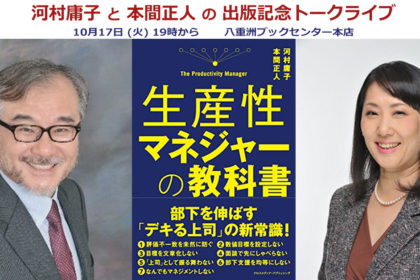11大学のファンドレイザー向けに「寄付獲得のためのホームページ作り~WEB上で寄付をしてもらうためのコンテンツ作りから、スマホ、SNSでは何をすれば良いか」の講義を行いました。

大学は国立も私立も自ら資金を集める努力が必要になっています。
東京大学や慶應義塾の寄付集めのお手伝いをしたことが縁となって、学術芸術領域での寄付文化・社会的投資文化を目的とする一般社団法人 Japan Treasure Summit (略称 JTS)のお手伝いを本間浩一が2013年からしています。
担当しているのは、大学のファンドレイザー養成プログラム「ファンドレイザーフォーラム」の「寄付獲得のためのホームページ作り~WEB上で寄付をしてもらうためのコンテンツ作りから、スマホ、SNSでは何をすれば良いか」という90分の講義です。
今年も2つのグループにそれぞれ講義を行います。10月12日の第一グループは11大学、次回は11月9日の第2グループです。
出身の大学が寄付集めをしているか、ご存じない卒業生がまだまだ多いのではないかと思います。
第1グループの皆さんの許可を得て、どんな大学の基金が参加しているかをご紹介します。(五十音順)
- 岩手大学イーハトーヴ基金
- 九州大学基金
- 京都大学基金
- KEK寄附金(高エネルギー加速器研究機構 )
- 東京大学基金
- 東京海洋大学基金
- 東京工業大学基金
- 名古屋大学基金
- 学校法人常翔学園 学園サポーターズ基金(大阪工業大学)
- 大阪電気通信大学への寄付
- 西南学院大学 サポーターズ基金
各大学からの参加者には事前に宿題を出して、自校の基金・寄付サイトのについてアクセスログの定量的な数値も含めて理解してきていただきました。先進事例として、充実した基金を持っている Stanford University と Harvard University のサイトのコンテンツや機能も参照しています。
11校の機関全体のHPと基金ページ、そして実際の寄付状況に関する講師の分析結果を示しながら、個々の結果や分析方法をレクチャーします。
基本事項としては次の2つを示します。
- 基金サイトへの流入元として、4つのチャネル別の解説
- 検索エンジン/具体的にどんなワードで検索されているか
- 他サイトのリンク/大学サイト等と基金サイトのリンクの状況
- SNS/主にfacebookからのアクセスについて
- 直接(メールなど)
- アクセスするユーザの、地域、デバイス(PC/mobile/tablet)、ブラウザの識別
また、今年重点的に扱ったのは、SSL対応やスマートフォン対応の程度によってどれだけご寄付が失われている可能性の指摘です。
毎年継続して各大学のウェブサイトの分析を行っているため、おのずとリニュアルによる変化も確認できます。指摘・アドバイスしたことが実際の改善につながっているではと実感するケースも増えてきました。